|
1 坂道 4.8度、6.6度、8.6度のそれぞれを登るのに必要とする力 2 みぞ 5cmを越えるのに必要とする力 (力の量の測定にはばねばかりを用いた) |
実験方法は車いすの前方部分にばねばかりをかけ、接地面にたいして水平に 引きそのときの力の大きさを計測した。 結果は以下の通りである。
| 車いすの重量 | 12kg重 | |
| 乗車した人の重量 | 60kg重 | |
| 1 坂道 | 4.8度 | 6.0kg重 |
| 6.6度 | 8.0kg重 | |
| 8.6度 | 12.0kg重 | |
| 2 みぞ | 5cm | 9.4kg重 |
| 最大静止摩擦力 | 15kg重 | |
それでは、分析をしていきたいと思う。
以下、変数は次のようにして表わす
| M | 全重量 |  |
| MF | 前輪にかかる重量 | |
| MB | 後輪にかかる重量 | |
| NF | 地面が前輪に加える力(=MFg) | |
| NB | 地面が後輪に加える力(=MBg) | |
| g | 重力加速度 | |
| f | 手すりに加える力 | |
| r1 | 後輪手すりの半径 | |
| r2 | 後輪の半径 | |
| rF | 前輪の半径 |
①車いすの前輪と後輪の重量比
とすれば
力学的モーメントから重心を中心として回転しないためには
 となる。よって
となる。よって


となるので

という比になる。

②静止している車いすを動かす 駆動輪である後輪について考える
水平方向への運動方程式は

また垂直方向は

これより加速度は

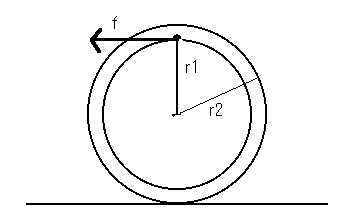
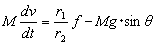
という条件が加えられる。
③斜面を登るとき
②の場合に、重力を加える水平方向の運動方程式は
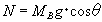
垂直方向は

となるので
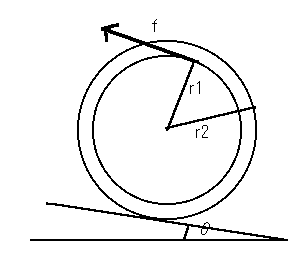
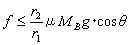
となるので、あわせて
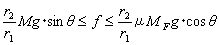
という条件のもとで前にすすむようになる。
④段差を登るとき
前輪が段差を越える条件は
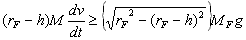

を代入して
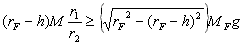
という条件で登ることができる。

さて、以上の分析から必要な力を算出してみる。
この時それぞれの大きさは
| 前輪の半径 | 7.5cm |
| 後輪の半径 | 30.0cm |
| 手すりの半径 | 25.0cm |
| 前輪、後輪の重量比 | MF:MB=1:2 |
とした。
| 障害物 | ばねばかり | 手すり |
| 坂4.8度 | 6.0kg | 7.2kg |
| 坂6.6度 | 8.3kg | 9.9kg |
| 坂8.6度 | 10.8kg | 12.9kg |
| みぞ5cm | 8.5kg | 10.1kg |
ということになる。
坂に関しては実験データとほぼ同じになった。
8.6度についてはばねばかりのはかりかたに問題があったように思える。
みぞは5cmと計測したはずであるが、ずれていたと仮定し、みぞ5.5cmとすると
| ばねばかり | 9.4kg |
| 手すり | 11.4kg |
となる。またこれ以外についても求めたので並べてみると
| 障害物 | ばねばかり | 手すり |
| 坂1゜ | 1.3 | 1.5 |
| 坂2゜ | 2.5 | 3.0 |
| 坂3゜ | 3.8 | 4.5 |
| 坂4゜ | 5.0 | 6.0 |
| 坂5゜ | 6.3 | 7.5 |
| 坂6゜ | 7.5 | 9.0 |
| 坂7゜ | 8.8 | 10.5 |
| 坂8゜ | 10.0 | 12.0 |
| 坂9゜ | 11.3 | 13.5 |
| 坂10゜ | 11.9 | 15.0 |
| 段差1cm | 13.8 | 16.8 |
| 段差2cm | 22.3 | 26.7 |
| 段差3cm | 32.0 | 38.4 |
| 溝幅3cm | 4.9 | 5.9 |
| 溝幅4cm | 6.6 | 7.9 |
| 溝幅5cm | 8.5 | 10.1 |
| 溝幅6cm | 10.5 | 12.6 |
| 溝幅7cm | 12.7 | 15.2 |
| 溝幅8cm | 15.1 | 18.2 |
| 溝幅9cm | 18.0 | 21.6 |
| 溝幅10cm | 21.5 | 25.8 |
坂やみぞに比べて段差の力が多く必要であることが目に付くが、これはあくまで水平方向のみの力である。ここで重心を後ろにかける行為、つまり「背もたれに背中をつける」ことで、前輪にかかる負担を減らすことができるので負担はもう少し少なくなると考えられる。以上の結果とアンケート結果を見比べて欲しい。段差3cmがなぜアンケートで一番の難度を示したのがおわかりいただけるはずである。今後この結果が車いす利用者のための社会づくりに役立てていただければと思う。